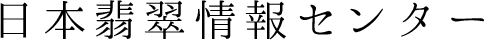ANCIENT HISTORY
オオクニヌシは勾玉貿易によって財をなした
 縦に約80ミリ、重量250g、てのひらにずっしりとくる日本翡翠大勾玉。オオクニヌシの時代にはこんなに大きな勾玉を作れる技量はなかった。もしかの時代に持っていけたら、たちまち王になれたことだろう
縦に約80ミリ、重量250g、てのひらにずっしりとくる日本翡翠大勾玉。オオクニヌシの時代にはこんなに大きな勾玉を作れる技量はなかった。もしかの時代に持っていけたら、たちまち王になれたことだろう
 頭部に3本の刻みを入れた丁字頭(ちょうじかしら)勾玉は、イルカが笑っているようであり、精霊たちの言葉を伝える勾玉だったようにも思える
頭部に3本の刻みを入れた丁字頭(ちょうじかしら)勾玉は、イルカが笑っているようであり、精霊たちの言葉を伝える勾玉だったようにも思える
 ギョロメ勾玉は大きな眼で「魔」を防ぐ魔除けの勾玉。「魔」は気のゆるみを狙って襲ってくるので、気がゆるんでも大丈夫なようにしておくことが肝要
ギョロメ勾玉は大きな眼で「魔」を防ぐ魔除けの勾玉。「魔」は気のゆるみを狙って襲ってくるので、気がゆるんでも大丈夫なようにしておくことが肝要
 糸魚川市の金山谷というところで採集される翡翠原石には不思議な色合いをしたものがある。鎮魂の力が強いようだ
糸魚川市の金山谷というところで採集される翡翠原石には不思議な色合いをしたものがある。鎮魂の力が強いようだ
 オオクニヌシ神話のなかで勾玉には鎮魂の役目が加わる。タテガミは大きな力が宿ってのパワーの放射を象徴している
オオクニヌシ神話のなかで勾玉には鎮魂の役目が加わる。タテガミは大きな力が宿ってのパワーの放射を象徴している
[18]日本神話における天上界から地上界への移行
これまで眺めてきたように、勾玉は日本神話では、特別なパワーオブジェクトの扱いを受け、大和王朝の始祖となった一柱の神は勾玉から生まれたとされ、天皇の証しとなる三種の神器のひとつに数えられました。
『古事記』『日本書紀』が伝える神々の物語は、アマテラスの岩戸隠れにつづいて、スサノウを高天が原から追放することで、舞台は地上の出雲に移ります。肥河(ひのかわ)の川上の鳥髪(とりかみ)という土地に降りたスサノウは八俣の大蛇(おろち)を退治し、子孫をもうけた後に、地下世界である根堅洲国(ねのかたすのくに)に赴きます。(八俣の大蛇は字義通りなら首の又が8つ、ならば頭は9つだったかもしれないところに中国神話の影響があって愉快)。
ここに地上世界・芦原中津国の支配者へと成長していくオオクニヌシが登場してきます。オオクニヌシ(大国主命)には、オホナムヂノカミ(大穴牟遅神)、アシハラシコヲ(葦原色許男神)、ヤチホコ(八千矛神)、ウツシクニタマ(宇都志国玉神)などの別名があり、国津神の代表者となってからオオクニヌシとよばれるようになりました。中津国の支配者にふさわしい名前です。
ちなみに彼の故郷で編まれた『出雲風土記』にはオオクニヌシに該当する神はオオナモチ(大穴持命)と呼ばれ、オオクニヌシの呼称はありません。オオクニヌシは記紀神話を記すにあたって中央で創作された名前です。
記紀の編纂者たちが、古代中国の理想的な王朝交代劇を模して、アマテラスの子孫である天孫族は中津国を侵略・征服して大和王朝を建国したのではない、先住民の王家から「禅譲」を受けて新たな支配者となったのだ、という筋立てにしたと思われます。
後々見ていくことになりますが、古代の大王たちは、西欧の例からするなら、侵略・征服王朝を建てたとしか思えないようなケースでも、建て前上は前王家に婿入りすることで王朝を継いでいきます。「禅譲」と「婿入り」が王朝交替のキーワードだったようです。ともかくもそうして、理想的王朝交代劇を演出・記述するために、記紀の編纂者たちは、オオクニヌシという敵方の立て役者を必要としました。
青年時代のオオナモチは、因幡の白兎を助けたり、多数の兄弟神・八十神(やそがみ)に殺されかけたりして、ついには根の国にスサノウを訪ねます。スサノウの娘のスセリヒメと相思相愛となったオオナモチは、スサノウが与えた試練のことごとくを退け、スセリヒメとともに、スサノウの宝を奪って、地上世界・中津国に戻ります。娘婿となったオオナモチにスサノウは告げます。これからは大国主神と名乗り、また宇都志国玉神(うつしくにたま)となって、出雲に巨大な宮殿を建て、わが娘のスセリビメを正妻として天下を治めよ、と。
このあと『古事記』では、オオクニヌシの多数の神妃による子孫の繁栄、一寸法師ほどに小さなスクナヒコナと共同しての建国、スクナヒコナが去ってのちは三輪山の神オオモノヌシの助力による国つくりの完成へと、物語は移っていきます。
天上世界・高天原から地上世界・中津国の繁栄ぶりを眺めていたアマテラスは権力者の常で、この豊かな土地を欲しくなり、オオクニヌシに国譲りを迫り、自身の孫を降臨させて大和王朝を建国していく。と、このようなところが日本神話の粗筋です。
アマテラスを代表とする天上界の神々を「天津神(あまつかみ)・天神(てんじん)」と呼ぶのに対して、オオクニヌシを代表とする地上界・中津国の神々を「国津神(くにつかみ)・地祇(ちぎ)」といいます。両者を合わせて天神地祇(てんじんちぎ)で、列島の神々は数えきれないほどに多いので、その数は八百万(やおよろず)と表現します。神々が八百万もいるのだから、日本人はみんな祖先が列島の神々か、歴史時代になって朝鮮半島や江南あたりから移民してきた向こうの神々の子孫ということになります。
[19]オオクニヌシと大黒さまは同じ神様
オオクニヌシ(大国主命)は大黒さまとよんだほうが親しみやすいでしょう。大きな袋をかついで、金銀財宝をザクザクと生む打出の小槌を持ち、米俵の上にたって、たいがいは鯛を抱いた恵比須さまといっしょに祭られる、あの大黒さまです。ちなみに米俵には仏教の影響であらゆる願いをかなえる如意宝珠が描かれています。
オオクニヌシと大黒天との同一視は、平安時代初期にはじまった神仏習合の影響によります。仏教の影響力が大きくなって、日本の神々は仏教の仏たちが、日本という風土に合うよう神々の姿をとって現れたとする考えが普及しました。これが神仏習合で、その時代列島各地の神々は、自分の神社の巫女に神懸かりして、自分にも仏教徒としての名前が欲しいと告げたりしました。こうして現在に残るような○○明神、△△権現という仏教名を持つ土着神や山岳神が出現することになったのです。
大黒天はもとはインドのシヴァ神の変化身(へんげしん)のひとつでインド名をマハカーラ(大きな黒)といいます。マハカーラは大乗仏教に取りこまれて仏法の護法神の一柱となりました。詳しくは知らないでいるのですが、古代中国でシヴァ神の息子で象頭人身のガネーシャと同一視されたらしく、寺院の厨房に祭られる食物神になりました。本来の大黒天は怒れる死神でとても厨房に祭られるような神ではありません。やがて列島に伝来して、食物神であることと、大黒と大国の音が同じであることから、オオクニヌシは大黒天と同体とみなされるようになりました。
オオクニヌシは港々(津々浦々ともいう)に妻を持つ艶福の神さま。これにあやかって大黒さまは縁結びの神様となり、道祖神に見られるような性器信仰の影響下で、後ろ姿を男性器に見立てた立像も作られるようになりました。
大黒天といっしょに祭られる恵比須神にも習合の歴史があります。エビスは元来はクジラやイルカ漁に関連した海の豊穣神であり、海の彼方から幸運・財宝を運んでくる神だったようです。この神とイザナギ・イザナミの最初の子供ヒルコが同一視されました。日本神話ではヒルコは奇形児であり未熟児の扱いを受けていますが、縄文時代的な感性では、パワー的な世界に属するものが十分に物質化していない未分化な状態をあらわしていたと思います。彼は形を整えて、より立派な姿となって戻ってくることを期待されたようです。
エビスとヒルコが合体したところに、オオクニヌシの長男コトシロヌシが習合しました。彼は釣りにでかけた先で、高天原からの使者による国譲りの要請を受け、承諾してそのまま海中に隠れてしまいます。もとはといえば大和地方の神で出雲とは縁がないのですが、記紀の編纂者たちが大和王朝建国以前の地上世界をオオクニヌシ一族の支配地として描きたがったゆえに、出雲系の神にされたといわれています。こうして大黒恵比須は親子神としていっしょに祭られるようになり、さらには七福神の代表として、惜しげもなく富を授ける神になりました。
[20]オオクニヌシとヌナカワヒメの求婚譚
勾玉に関連したオオクニヌシ神話の白眉は、日本翡翠の原産地である越(こし)、いまの北陸地方のヌナカワヒメへの妻訪いで、美しさと悩ましさ、呪術的色彩の濃さでこれに勝る恋物語は日本神話に見当たりません。
またこの神話をもって日本翡翠の研究者の多くは、卑弥呼とほぼ同じ時代の出雲の勢力は翡翠原石を掌中におさめたくて新潟富山県一帯を支配下に組み入れたと考えています。
ヌナカワヒメのヌナカワは「ニの川」の音韻が変化したものとされています。ここでのニはニニギのニ、八尺瓊勾玉のニと同じ「光り輝く宝石」を意味します。ヌナカワは当て字すれば沼河、布川、奴奈川となっても意味は宝石の採れる川の意味で、ヌナカワヒメは宝石が採れる川がある土地の姫、もしくは川の女神になります。こうした伝説があって現在の糸魚川市を流れる川は姫川とよばれています。
ヤチホコはオオクニヌシの別名とされていますが、弥生時代後期に活躍した出雲西部の人たちが祭った英雄神で、すぐ後でふれることになる荒神谷遺跡の支配者だったようです
「ヤチホコノミコト(八千矛命)は越(こし・高志国)のヌナカワヒメ(奴奈川姫・沼河比売)に求婚しようと遠征されて、姫の家の前で次のようにお唄いになられました。」
と、物語は始まります。『古事記』のなかではもっとも艶のある物語で、越(こし)を征服したオオクニヌシの遠征譚といわれています。語り手はアマノハセヅカイという語り部です。宴会などで節回しも豊かに朗々と歌いあげたことでしょう。
「私は大八島の国々に妻にふさわしい女を捜してきた。はるかな遠方、越の国には賢い女がいる、美しい女がいると聞いて、矢も盾もたまらず、駆けつけ、訪ねてきた。船が港に着くやすぐさま、太刀(たち)の緒も解かず、かぶりものも脱がないで、こうして麗しい人が眠る家の板戸の前に立ち、なかにいれてほしいと、夜どうし乞い願っている。ああ、口惜しいことに緑の山にはヌエ(トラツグミ)が鳴き、野には雉が鳴いている。庭の鶏 (とり)がけたたましく鳴いて夜明けを告げている。いまいましくも鳴く鳥どもだ。いっそのこと鳥たちを殺して、夜がつづけと願おうか」
わたくし語り部のアマノハセヅカイ(天駈使)は、ことの起こりをこのように聞いています。さて、ヌナカワヒメはそれでもヤチホコノミコトに会おうとはなされず、板戸の内側からお応えになられました。
「ヤチホコノミコト(八千矛命)よ、私はか弱い女ですから、心は入り江の鳥のように強い男を求めています。いまは自分勝手な鳥のようでも、のちにはあなたに従う鳥になりましょう。どうか鳥たちを殺さないでください。青山に日が隠れればぬばたまの夜がまたきます。今宵にはきっとあなたをお迎えしましょう。そうしたら私の白い腕や、柔らかくはりつめた乳房を可愛がり愛撫して、思いのままにお過ごしください。そして私の玉のような手を枕にお休みになられますものを。どうか、そのようにことを急がないでください」
わたくし語り部のアマノハセヅカイ(天駈使)は、語り事をこのように聞いています。そしておふたりはその夜はお顔を会わせず、翌日の夜をともに過ごされたそうです。
ここでは、日本が家父長制へと移行する前の、女にも男を選ぶ力があった時代の、よばいの応答をみることができます。よばいは夜這いではなく、互いの名前をよばわりあったから、よばいというようになったといいます。その時代、名前には霊的な力があり、相手に本名をあかすのは呪術的に受容しあう証しとされていました。
[21]糸魚川地方のヌナカワヒメ伝説
「古事記」ではそのあと二柱の神は末永くよりそったのか、短期間の恋愛沙汰で終わったのか、いっさい語られていません。
ヌナカワヒメは地方限定の女神として祭られ、日本中からの注目を集めはしませんでした。ヌナカワヒメを翡翠の女神とする伝説も現地には残っていません。奈良時代以降翡翠文明そのものが忘れられ、原産地にあっても翡翠を知る人が途絶えてしまったのだから当然のことです。平安時代以降の文化の影響のようですが、糸魚川地方に残るヌナカワヒメ神話の多くは『古事記』の母系的で自己主張のある女性ぶりとは裏腹に、父系文化風で身勝手な男に翻弄された姫の物語となっています。
『出雲風土記』ではヌナカワヒメは港の守護者の娘であり、出雲へ連れられていって、ミホススミ神を生んだと伝えられています。けれど地元の伝説では彼女はオオクニヌシから逃れるのに必死です。
『古代越後奴奈川姫伝説の謎』(渡辺義一郎、1978)という本には、山ほどのヌナカワ姫伝説が収録されています。ヌナカワ姫は黒姫ともよばれ、姫にちなんで糸魚川を中心に3つの黒姫山があります。その近辺にはヌナカワ姫を祭った数多くの神社があるのですが、オオクニヌシとヌナカワ姫の恋の結末を祝う伝説は少なく、オオクニヌシに嫁ぐのが嫌で、姫川沿いに逃げる話が多いのです。
姫へのオオクニヌシの求愛に地元の男も黙っていません。
「根知谷別所山に牛の爪痕が三つ刻まれた岩と、馬の足跡の一つ刻まれた岩とがある。昔奴奈川姫に懸想した土地の神が、大国主命が来て姫を娶ろうとしたのを憤り、論争した結果、山の高所より飛びくらべをして勝った者が姫を得ることにした。土地の神は黒き青毛の駒に跨がり、大国主命は牛に乗って、駒が岳の頂上に立った。まず土地の神が神馬に鞭をあてて飛んだところ、馬の足跡が残っている場所まで飛んだ。次に大国主命が牛を励まして飛ぶと、それより2、3町(1町は約110メートル)先の地点に達した。これが今日なお牛の爪痕のある場所である」(前掲書、p265参照)
あるいはまた、
「姫川の上流の松川に姫ヶ淵という深い淵があるが、ここは大国主命の手先に追われた奴奈川姫が進退極まって身投げした場所なので、姫ヶ淵というようになった。姫川の名もこれから出たという」
平安時代に編まれた偽書とされる『旧事本紀(くじほんき)』では、諏訪大社に鎮まる軍神・タケミナカタは、オオクニヌシを父にヌナカワ姫を母に誕生したとします。今日、糸魚川市を訪ねると目につくヌナカワヒメの母子像は、この説話をもとにしています。ヌナカワヒメが翡翠の女神になったのは新しくて、経済の高度成長時代に日本中が総観光地化して以来のことのようです。1500年の時を経てよみがえった日本翡翠同様、翡翠の女神の復権は古代の息吹の再誕を告げているようで頼もしいかぎりです。
[22]出雲大社所蔵の翡翠勾玉の謎
青年時代には益荒男(ますらお)としてとおし、壮年時代には偉大な建国者・支配者だったオオクニヌシも、老年にはいるとパワーが衰えたようです。高天が原から派遣されてきた敵軍になすすべもなく国譲りを承諾して、『日本書紀』では身に大きな勾玉を付けて、『古事記』では天上界の宮殿のような、大空に千木(ちぎ)を高々とそびえさせた宮を作って自分を祭るよう要請して幽界に降りていきます。
ここでの勾玉は王位継承の品や、祭祀権を象徴する品とは意味が異なります。祖霊の力を身に付けてパワーアップをはかる勾玉でもありません。魂を慰撫する鎮魂の勾玉です。
現代では鎮魂は死者の魂を鎮めて安らがせるという意味でしか使われませんが、古代には精神的不安、動揺などが原因となって、魂は身体から離れやすいと考えられていて、身体の内に魂を安住せしめて、心を安定させるのが鎮魂の意味でした。鎮魂は生者においても死者においても、魂を鎮めて霊力の衰退を防ぐ技であり、心が荒らぶって猛り狂わないよう、死者にあっては祟らないよう気持ちを鎮めるやることが重視されていました。鎮魂の勾玉は高塚式墳墓(前方後円墳)への勾玉副葬につながるものであると考えられます。
古代の出雲にはたくさんの謎があって、ひとつの謎を追うと新たな謎に直面するようなところがあるのですが、オオクニヌシが自死にさいして身に付けた勾玉をほうふつとさせる日本翡翠の勾玉が、祭祀跡と想像できるところから出土しているのも、驚嘆すべきことがらのひとつです。
問題の勾玉は、いまは出雲大社の宝物(ほうもつ)となっている、長さ35ミリほどで、世にも美しい翡翠のギョロメタイプの勾玉です。科学的分析の結果、富山・新潟の県境地方産出の日本翡翠原石からの加工品であるとされていますが、なぜそれがまるでオーパーツのように1個だけ、出雲に埋められていたのか不思議でなりません。
この勾玉は1665年(寛文5年)、出雲大社の境内から徒歩5分のところにある命主社(いのちぬしのやしろ)の背後の大岩の下から、長さ約30センチの銅戈とともに発見されました。銅戈(どうか)は棒の先に直角に取りつけて用いる、握り棒の長い鎌(かま)のような武器ないし武器型の祭用具。出土品の銅戈は荒神谷遺跡出土の銅矛(ほこ・ヤリ状の武器で祭祀用品)と同じ系列と見られています。
銅剣・銅矛は朝鮮半島から武器として伝わったのが、おもに北九州で祭祀用品として大型化するなど、独自の発達をとげました。青銅製品と鉄器が列島にほぼ同時に伝わって青銅器の実用価値が薄れたことと、鋳造したての青銅製品は金ピカに輝いて神々しく見えるせいとされています。
1665年は江戸時代の初期で、4代将軍徳川家綱の時代に相当します。出雲大社の造営に役立てようと、命主社の裏の大岩を石材として切りだす最中に発見されたといいます。 埋納の時期が弥生時代後期の荒神谷遺跡発生に前後するなら、その時代には出雲大社は存在していませんでした。
いろいろ調べても具体的な年代をみつけられませんでしたが、神々の住まいとして神殿が建設されるようになるのは、古代インドの例から推定して、仏教の伝来以降のことのようです。それまでは神は儀式ごとに招いて、祈願し、饗応して、お帰りいただく存在だったようです。神々が降臨する神籬(ひもろぎ)や岩座は聖域として神聖視されていました。屋敷内に神祭りの場所はあっても、神がこちら側に定住するという発想はなかったと思います。古代インドでヘレニズムの影響のもとに、まずはガンダーラ地方で、仏像が作られるようになったのと同じように、日本列島に仏教経典とともに仏像が伝来すると、仏像に宿る仏のための住居が必要になり、朝鮮半島の様式を真似て寺院が建立されるようになりました。その影響のもとに、神道でも神々のための住居を必要とするようになり、神々は神殿に常駐すると考えられるようになったようです。神道は神代(かみよ)の昔からあったにせよ、神社建築の始まりは比較的新しい出来事です。
さらにまた、勾玉の故郷のように思われている出雲ですが、出雲大社のある杵築地方から東に離れた玉造温泉地方で、同地の花仙山の碧玉(グリーンジャスパー)を使用した勾玉が製作されるようになったのは、弥生時代終末期のことで、しかもこの地方の玉作り遺跡で日本翡翠の勾玉が作られた形跡は一切ありません。ですからあの勾玉は出雲で作られたものでないことは明白です。
弥生時代の後期や末期には、巨石は盤座(いわくら)として神聖視されていたはずで、戦勝や飢饉の終焉を願って氏族の神宝を捧げたとか、氏族間の戦争に敗れて逃亡するにあたって氏族継承の品を埋めた、などのケースが考えられます。奉納者は後出のヤチホコ信仰にゆかりのある人たちだったことでしょう。
この勾玉はロウカン質で透明度の高い深緑色の日本翡翠で作られていて、あまりに立派なので、自分としてはこれが弥生時代に作られたという説に、素直に納得できない気持ちでいます。
記紀の物語りでは崇神天皇などが活躍する初期大和王朝時代には、オオクニヌシやその分身とされるオオモノヌシはしばしば祟る神となって登場します。出雲大社のあの勾玉もヤチホコとよばれていた神を鎮める儀式に使用されたものであるようにも思えます。
[23]荒神谷遺跡&加茂岩倉遺跡とヤチホコ
神話伝説に歴史の投影はあるのかないのか、といった魅惑的なテーマは、出雲においてはがぜん現実的な輝きを放つようになってきています。
神話や伝説は過去の記憶をもとに、社会的な無意識によって脚色され、姿を変えながら伝承されていきます。古い時代の出来事の記憶がさほど歪曲されずに持ち越されることもあれば、天変地異や社会変動、政権交代などによって古い時代が捏造、もしくは創造される場合もあります。それでも火のないところに煙はたたないわけで、神話や伝説にはそれの元となったなにがしかの出来事があったのだと、考えたくなります。
第二次世界大戦後日本の古代史学界は、オオクニヌシ神話は、天孫族による建国神話をひきたてるために日本神話に組み入れられたものである、出雲は名ばかりで彼の地に大きな勢力はなかったとしてきました。ヤチホコの妻訪いも『古事記』に加えられた古い歌謡のひとつと片付けられてきましたが、出雲での考古学的発見があいつぎ、そうもいっていられなくなりました。
以下では神話伝説とシンクロする出雲の歴史を眺めていくことになります。ヤチホコを信奉したであろう集団が残した驚天動地の遺跡を眺めたり、ヤチホコとオオナムチは別人格の神だったことに触れたりします。八雲たつ出雲は神々のふるさと。出雲へ行って、玉造温泉などを訪ねると、出雲は勾玉のふるさとのようにもみえますが、なぜそのようなことになったかについても話をすすめたいと思います。
昭和50年(1984)に出雲の荒神谷遺跡から358本もの銅剣が発掘され、翌年には銅矛16点、銅鐸6点が発掘されています。それまでの弥生時代の銅剣の現存数は300本余りだったので、この出土数は考古学的驚異でした。さらに驚くべきことに1996年(平成8年)には、荒神谷遺跡から直線距離で3.5キロメートルの加茂岩倉遺跡から1ヶ所の出土量としては全国最多、39個の銅鐸が発掘されました。
荒神谷遺跡は弥生時代中期後葉、加茂岩倉遺跡もほぼ同時期、中期後半から後期初頭の遺跡とされています。この時期は卑弥呼の時代にほぼ重なり、大和王朝の始まりと推測されている時期、古墳時代の始まりである紀元3世紀の後半あたりともほぼ同じになります。
銅剣・矛文化圏は北九州にあって、銅鐸文化圏は近畿・中部にあったとする、旧来の弥生時代の文化圏の色分けは両遺跡の発見によって色あせてしまいました。
考古学的に明らかにされつつあるように、この時代の日本列島には、日向・北部九州・吉備・北陸(越・こし)・近畿など、それぞれがひとまとまりの文化圏ができていました。そうしたなかで、北九州の銅剣と近畿・中部の銅鐸を、他に類がないほど大量に収集することができた国家的存在が出雲にあった、と考えざるを得なくなったのです。
これらの遺跡からの出土品によって、オオクニヌシに代表される一族が出雲で権勢を誇ったことが推測されますが、かといって大和王朝以前に北部九州から近畿地方一帯を征服した王国があったとの痕跡を見つけにくいので、出雲の民はこれらの土地を交易圏としていたと考えるのが妥当なようです。
『増補改訂・勾玉』(水野祐、学生社、1992)には以下のようにあります。
「荒神谷遺跡のある土地は、古くは神門臣(かんどのおみ)という豪族の勢力下にあった。神門臣は祖神として、八千矛を祭っていた。神門臣の西出雲の勢力は、弥生時代から古墳時代にかけて、しばしば東出雲の大庭を中心とする出雲臣族(のちの出雲国造)の勢力と抗争を繰り返した。この抗争は『古事記』では倭健命の出雲健(たける)征伐として伝え、『日本書紀』では崇神朝の出雲振根(神門臣側)討伐の物語としてとらえている。 結果的には意宇の勢力が大和の勢力と妥協して杵築(きつき)の勢力を屈伏させて、出雲は5世紀には、出雲臣(出雲国造家)の手で統合されたと考えられる。」p-193
「西出雲の杵築の八千矛を祭る豪族神門臣と、東出雲の意宇の大穴持神を祭る豪族出雲臣族とは元来血縁関係がなく、神門臣の振根が滅亡したとき、系譜的擬制によって両者の同族関係が成立した。八千矛は大穴持神の別称として同一視された。」p-193
「西出雲は早くから八千矛の銅剣・銅鉾の崇拝者の集団であり、その祖神の后神は宗像の3女神の1柱である多紀理毘売命であり、宗像と出雲杵築との深い関係が示唆されている。」p-193
矛(ほこ)は槍に似た武器です。弥生時代には青銅製の矛が武器としてではなく、祭祀用に多数製作され、形状も大型化していきました。当時実用的な武器としては鉄器がありました。鋳造したての青銅は赤金色に神々しく輝いたから神々への供物となり、依り代となったのです。
日本神話のはじめのほうで、国生みの夫婦神イザナギとイザナミが天の浮橋に立って、混沌とした海に指し降ろす天の沼矛(ぬぼこ)は、ヌナカワヒメの「ヌ」と同じ、宝石のように華麗な矛をいいます。
荒神谷と加茂岩倉、ふたつの遺跡からの膨大な量の出土品を前に、これらがどこから来たかを考えるなら、山陰や北陸で作られた管玉や勾玉を北部九州に運んだのは、ヤチホコを英雄神とあおぐ西出雲の民だった可能性が見えてきます。玉製品との交換には青銅や鉄がもちいられたことでしょう。そうやって彼ら交易の民は、山陰・北陸・近畿地方を行き来して財を蓄え、勢力圏を拡大していったと想像できます。
あえて歴史にあてはめるなら、ヤチホコがヌナカワヒメに妻訪したのは、卑弥呼の活躍や初期大和王朝の建国とほぼ同じ時代のことになります。当時はヤチホコを信奉する杵築地方の西出雲のほうがオオナモチを擁する意宇地方の東出雲より勢力が強く、東出雲で勾玉の製作は始まっていなかったし、東出雲と北陸との交渉はなかったようです。そのせいで出雲に糸魚川地方産の日本翡翠原石は持ち込まれなかったと考えられます。
記紀の編纂者にとっては国譲り=禅譲の構図を確立することのみが大事で、出雲の歴史は圧縮されて、国譲り一本にまとめられたと解釈できます。
初期大和王朝が誕生して勾玉信仰を受容したために、神話では勾玉ははなから天孫族のパワーオブジェクトとされていますが、歴史的にみるなら勾玉は中津国で発展した呪具・物実(ものざね)で、ヤチホコ=オオクニヌシとその仲間たちに属していたと考えられます。