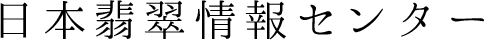ANCIENT HISTORY
南九州から大和へ天孫族は長征してきた
 天孫降臨につづく日向三代は、神々から人間へ、神話から伝説へと移行する過渡期の物語で、奈良時代の風潮を反映して、勾玉は仏教説話風の「玉」に置き換えられている。写真は昔話の「玉」にイメージが近い大型カボーション・カットされた大型スター・ミルキークォーツのルース。直径53ミリ、高さ33ミリ、重量約600カラッツ(120グラム)
天孫降臨につづく日向三代は、神々から人間へ、神話から伝説へと移行する過渡期の物語で、奈良時代の風潮を反映して、勾玉は仏教説話風の「玉」に置き換えられている。写真は昔話の「玉」にイメージが近い大型カボーション・カットされた大型スター・ミルキークォーツのルース。直径53ミリ、高さ33ミリ、重量約600カラッツ(120グラム)
 古代中国では玉(ぎょく)はおもにネフライトで作られた璧(へき)やソウなどの彫刻作品を意味した。そうした伝統とは別に、龍神の気息のうちに析出すると想像された如意宝珠があった
古代中国では玉(ぎょく)はおもにネフライトで作られた璧(へき)やソウなどの彫刻作品を意味した。そうした伝統とは別に、龍神の気息のうちに析出すると想像された如意宝珠があった
 如意宝珠のパターンのひとつが擬宝珠(ぎぼうし)型をして先端が尖った球。魂振りによって魂が励起した瞬間を表現している
如意宝珠のパターンのひとつが擬宝珠(ぎぼうし)型をして先端が尖った球。魂振りによって魂が励起した瞬間を表現している
 宮崎県串間市王の山古墳から出土した玉製璧(ぎょくせい・へき)。径333ミリ、重量1600グラム。『日本の古代史2・列島の地域文化』(森浩一編、中央公論社、1986)から転載。
宮崎県串間市王の山古墳から出土した玉製璧(ぎょくせい・へき)。径333ミリ、重量1600グラム。『日本の古代史2・列島の地域文化』(森浩一編、中央公論社、1986)から転載。
 山東省広州市の南越王墓から出土した玉製璧(ぎょくせい・へき)。璧としては最大級のもので径334ミリある。『西漢南越王墓博物館収蔵品図録』からの転載
山東省広州市の南越王墓から出土した玉製璧(ぎょくせい・へき)。璧としては最大級のもので径334ミリある。『西漢南越王墓博物館収蔵品図録』からの転載
[24]天孫族は出雲を忘れ日向の峰に天降る
『日本書紀』と『古事記』には、およそ2600年前に、南九州から出てきた神武天皇が大和(奈良)に、日本で最初の王国を建国したと書いてあります。以来現代に至るまでこの王朝は一度も血筋が絶えることがなかったとして万世一系といいます。
神武天皇の曾祖父はアマテラス大神の孫にあたり、孫が高天原から降りてきたので、天孫降臨といい、神武天皇が属する一族を天孫族とよんだりします。
天皇の漢字の称号は天武天皇以降に付けられたので、それ以前の大王たちを天皇名で呼ぶのは適切ではないかもしれません。けれど長くて古めかしい大王名それぞれに解説をつけるのは繁雑に過ぎるので、以下では天皇名で表記していきます。
あるとき天上界・高天原の主宰神であるアマテラスが地上界・芦原中津国を見下ろします。雲間から垣間見える大地が富栄えていることを知り、わがものにしようと欲するところからこの物語は始まります。最初に偵察のためにスパイを送りこむのですが、彼らはオオクニヌシになびいて任務放棄する始末。結局は武力で威嚇してオオクニヌシを幽界に追いやります。
支配地の総督に任命されたアマテラスの息子・アメノオシホミミ(天之忍穂耳命)は下界をみて蛮族ぶりに嫌気がさし、生まれたばかりの自分の子供に役目を押しつけます。
こうして日本神話は天皇の歴史へと移っていくのですが、どうしたわけか、出雲はそのまま放置されます。地上界を植民地にするのであれば、中心地である出雲に進軍するのが当然であるのに、国譲りなどなかったかのように、天孫族はオオクニヌシ一族とは何の関係もない日向に天降りして物語は展開していきます。
以下では日向三代の粗筋をおさらい程度に記述して、高天原からつづいてきた『古事記』と『日本書紀』の神話部分を終了したいと思います。
その1は初代のヒコホノニニギ(日子番能邇邇芸命)。彼はアマテラスの勾玉から生まれた彼女の息子、アメノオシホミミ(天忍穂耳命)の長男。親子ともに名前にホ(穂)があるところから、古代の天皇は天降(あまくだ)る穀物神だったとされています。天神が稲妻となって天降り大地の女神と交わることで穀物が実るわけです。
天皇の呪力・霊力があるからこそ、日本列島は穀物が豊かに実る瑞穂のクニとして存続できる、とのイメージ作りが功を奏して、世界に類をみないほど長きにわたって天皇制がつづいてきたようです。ホノニニギは5つの氏族を従えて、日向の高千穂の峰に天降りました。先導したのはアメノウズメ(天宇受売神)という女性シャーマンであったというのは非常に興味深い設定です。
古代には日向は南九州一帯の地名でした。日向三代の王たちは現代の宮崎県のみでなく、南九州を舞台に活躍します。ホノニニギは笠沙の御前(みさき、薩摩半島の西端あたり)で、山の神であるオオヤマツミ(大山津見神)の娘、カムアタツヒメ(神阿多都比売)、別名がコノハナノサクヤヒメ(木花之佐久夜毘売)と出会い、彼女を娶ります。生まれた子供は長男がホデリ(火照命)、通称が海幸彦、次男がホスセリ(火須勢理命)、三男で末っ子がホオリ(火遠理命)、別名がヒコホホデミ(日子穂穂手見命)、通称が山幸彦です。
漁夫になった海幸彦と狩人になった山幸彦は、ある日仕事を取り替えて、山幸彦は兄から借りた釣針を紛失してしまいます。いかように謝ろうと許してもらえず、兄はあの釣針を返せの一点張り。困惑しきっていると、シオツチ(塩椎神)という老人が登場して、山幸彦を竜宮へと送ります。その土地でワタツミ(綿津見神、海神)の娘トヨタマヒメ(豊玉毘売)と結婚して3年間を過ごします。
山幸彦は故郷が恋しくなり、帰還を申し出ると、海神は紛失した釣針を捜してくれ、塩盈珠(しおみつたま)で攻めてくる兄を溺れさせ、兄が降参すれば塩乾珠(しおふるたま)で水を引かせるよう、ふたつの宝珠を与えます。
故郷に帰って兄を服従させた山幸彦は日向三代のうちの二代目の王になります。そこへ豊玉姫が妊娠したといって訪ねてきます。天津神の子供は海神のクニで生むべきではない。ここに産屋を作って出産しようと思うが、決して産屋を覗かないと約束してくれといいます。
しかしこういう物語では男は覗き見すると相場が決まっています。トヨタマヒメは本来の姿である大きなサメにもどって出産の苦しみに七転八倒していました。
生まれた子供が三代目のウガヤフキアエズ(鵜葺草不合命)で、トヨタマヒメは正体を見られたことを恥辱に感じてクニに帰り、妹のタマヨリヒメ(玉依毘売)を地上に送ってわが子の乳母としました。
ウガヤフキアエズは成人して叔母のタマヨリヒメと結婚し、生まれた子供のひとり、末っ子のワカミケヌノ(若御毛沼命)が、のちに東征して大和王朝を開設したと記紀神話にある神武天皇です。ワカミケヌノにはトヨミケヌノ(豊御毛沼命)、またはカムヤマトイワレヒコ(神倭伊波礼毘古命)の別名があります。
[25]日向から古代中国の宝器が出土する不思議
日向三代の物語は、現代では昔話扱いされていて、歴史の投影があると考えられていません。記紀を読んでも、首長が婿入り婚を重ねることで存続できた小さな部族集団のようにみえます。三種の神器も忘れられていて、日向三代の物語は付け足しのようにも思えます。
神話の構図に目をとめるなら、天孫降臨というモンゴルやシベリアなど北方色の濃い神話ではじまりながらも、竜宮を訪ねてワニザメと結婚するなど、南方色に彩られた神話に始終します。江南のほうから伝わった神話と、モンゴルのほうから朝鮮半島を経由して伝わった神話体系をむりやりひとつにして大和王朝の起源としたような印象があります。
しかしそれでも、記紀の編纂者と当時の王朝の主宰者にとっては、大和王朝建国の由来を、こうした形で記録しておきたい理由があったはずです。それが何であったのかを考えはじめると、謎が謎をよぶばかりです。
神話時代、つまり弥生時代から古墳時代の初期にかけて、南九州は文明化の遅れた僻地ではありませんでした。現代の宮崎県西都市には西都原(さいとばる)古墳群という九州地方最大で、近畿地方と比べてもひけをとらない巨大前方後円墳が残されています。こうした巨大墳墓を築造できるほどに経済的に発展し、首長による統治がすすんだ土地でした。
日向から大和への神武天皇の遠征は辺境の民が都を目指して出奔したのではなく、都に安住の地を得られなかった氏族が、一族郎党新天地を目指して、新らたな都を作る物語です。
日向(南九州)は(1)に貝輪の交易地だったことにおいて、(2)に古代中国の宝器である<璧(へき)>が出土していることにおいて、「天然石と古代史」の観点から興味をそそられます。日向三代の時代、南九州一帯は隼人という海人族の領地で、海幸彦と山幸彦の物語の海幸彦(ホデリ・火照命)が隼人の祖先神であるとされています。
貝輪は沖縄など南の島々で採れるゴホウラ(護寶螺)、オオツタノハ、イモガイなどの大振りの貝殻を薄切りにした腕輪です。弥生時代の北部九州の人たちにとってはこれら貝輪は威信財であり、強力なパワーブジェクト、南の彼方にある不老不死のクニに再生するための切符だったようで、甕棺墓に副葬されました。貝輪の形は当時の人たちには強力なインパクトがあった模様で、青銅で類似品が作られ、古墳時代には近畿地方の前期古墳から、碧玉(ジャスパー)や緑色凝灰岩製の類似品が出土します。これらは考古学的には鍬形石、車輪石、石釧、などとよばれています。
南九州の隼人は、貝輪などの交易を手掛けることで、列島各地に居住地を拡散させていったと思われています。
「天然石と古代史」に興味を抱くと、出雲大社の日本翡翠勾玉と同じほど衝撃的な宝器が日向から出土していて息を呑むことになります。江戸時代に宮崎県串間市王の山古墳から出土した玉璧(ぎょくへき)がそれで、国宝になっています。
璧(へき)は中央に穴があるドーナツ状の円盤。天を祭る聖具として、5千年ほど前の長江流域の良渚文明に現われ、北に伝搬して周や漢の時代に権力の象徴になりました。皇帝一族と上層貴族の占有物であり、朝貢にいったくらいで下賜されるものではありませんでした。
串間市出土の璧は直径が333ミリ、重量1.6キログラム。璧としては最大級の大きさで、外側を龍が取り巻き、中央部は穀紋、内側に鳳凰が彫られています。
ほぼ同じ意匠、同じサイズのものが、広東省広州市の西漢南越王墓から出土していて、弥生・古墳時代が重なりあう時代に、江南と九州南部との間に通り一遍では済まない関係があったことを雄弁に物語っています。
南越国(前207-前111)は秦の滅亡期に、広東・広西省一帯を統治していた武将が建国した王国で、広州市に都をおき、100年ほどつづいて、5代目に漢に滅ぼされました。1983年に南越王2代目の墳墓が発見され、そこから死者に着せた玉衣(ネフライト・軟玉翡翠のタイル状小片を赤い糸で縫い合わせたもの)などとともに上記璧も出土しました。
弥生や古墳時代の中国文明の移入を論じるとき、中華4千年の華ともいえる玉(ぎょく)製品が、なぜ日本列島に伝わらなかったかが、疑問視されてきました。玉製品は権力者が天の庇護下にあることを保証する宝であり、製作工房も皇帝の支配下にありました。日本列島に移住してくるのは権力闘争に破れた者たちや、戦争による難民で、玉製品とは縁のない人たちでした。中国の朝廷は銅鏡あたりなら欲しがるだけ与えても、玉製品のようなパワーオブジェクトを東の蛮族に与えることはなかったと、想像されてきました。
それなのに、卑弥呼の邪馬台国とそんなに離れていない時代の日向に、秦か漢の時代に作られたであろう璧が持ちこまれていたというのは、三国志の時代に卑弥呼が朝貢した魏 (ぎ)に対して、江南の古代王国と連携のあった権力者が、日向にいたということを暗示しています。しかもこの権力者たるや王の象徴ともいえるほどに立派な璧を持つ身分だったのです。
短絡的発想を承知でいうなら、南越が滅びたとき、最後の王は幼児に璧を与えて、少数の従者とともに、南九州に亡命させたと、夢想したくなります。古代史的には根拠がないとされる日向三代の神話伝説は根も葉もない物語ではないのかもしれません。
[26]玉は勾玉を卒業して如意宝珠に変わっていく
日向三代では、玉の扱いがすっかりと南国風であり中国風なのも奇妙です。古代史や神話伝説に勾玉を追う試みは、ここでは異国の神話伝説の影響のもとに突然変異した玉の姿に戸惑うことになります。
玉には祖霊が宿らず、祭祀権の象徴ではなくなり、鎮魂の力を失ってしまいます。アラジンの魔法のランプや打ち出の小槌同様、呪文をとなえて玉をこすれば、意のままに願いがかなえられる如意宝珠であり、不老不死の妙薬になります。
『日本書紀』が編まれた奈良時代には、道教の神仙思想や仏教に押されて、古来からの玉の意味が失われてしまいます。『日本書紀』の編集に携わった官僚たちは、漢字の読み書きが堪能であることを条件に選ばれた渡来人の子弟が多かったといいます。彼らが列島の伝統文化に共感しなかったことも、玉に中国風だったりインド風の味付けがなされる理由のひとつです。彼らにはそれがどのような形であるのか想像できていなくて、龍の気息のなかに生じる宝珠=水晶球が、この時代以降、玉のおぼろな形となっていきました。
「玉磨かざれば光なし」とか、「玉石混交」の玉は、勾玉ではなく、形の定かではない想像の産物で、あえて例をあげるなら、如意輪観音や吉祥天の持ち物で、稲荷のシンボル、大黒天の米俵に記された宝珠になります。
山幸彦はもとはといえば自分に落ち度があるくせに、塩盈珠(しおみつたま)を手に呪文をとなえて攻めてくる兄を溺れさせ、兄が降参すれば塩乾珠(しおふるたま)で水を引かせて、兄を手下にしてしまいます。末子相続を正当化する説話とされています。この下りは神武天皇東征のおりに、先住の天孫族として登場するニギハヤヒ(饒芸速日命)の十種の神宝(とくさのかんだから)を連想させます。
ニギハヤヒは古代豪族の物部氏の先祖とされていて、『旧事本紀』という平安時代初期に編纂された書物にこの物語は記載されています。
ニギハヤヒは天孫族の証しとなる十種の宝物を持っていて、そのうち4種は、生玉・死返玉・足玉・道返玉という魔法の力を秘めた玉でした。生玉(いくたま)は生命力を増進させ、死返玉(しがえしたま)は死者を生き返らせる、足玉(たるたま)はあらゆる願いをかなえる、道返玉(ちがえしたま)は旅の安全を守るとか、身体から離れた魂をよびもどすと解釈されています。ここでも形状は勾玉か丸玉、棗玉あたりだろうと推測できるのですが、定かではありません。
ニギハヤヒ(饒芸速日命)に神宝を与えるにあたって、アマテラスは次のように語りかけたとされています。「もし痛むところがあれば、この十種の宝をして、ひと、ふた、み、よ、いつ、むつ、なな、や、ここのたりとかぞえて、ふるえふるえゆらゆらとふるえ、ととなえよ。そのようにすれば死者とて生き返ることだろう。これすなわちふるの呪文である」
玉を振るのは魂振りに通じ、波動ないし振動数をたかめてパワーを活性化することにつながります。魂振(たまふり)は沈滞・沈静している力の目覚めを意味していました。魂振によって穀物の種子・稲魂は芽吹き、神々や人もまた生命力や神秘的力を増幅・増大できました。
神々にしっかりと働いてもらうためには、なごみのうちにある彼らを目覚めさせ、パワーを増大してもらう必要がありました。古代の祭祀・呪術はそのために体系づけられた祈りの技法でした。玉が内在させているパワーを励起させるなら、魂に共振して、魂を活性化できたのです。
ヒコホホデミ(日子穂穂手見命、山幸彦)の妻のトヨタマ(豊玉毘売)や、ウガヤフキアエズ(鵜葺草不合命)に嫁ぐタマヨリヒメ(玉依毘売)という名前は、前者が玉(=魂)が元気で勢いのいい女性をあらわし、後者は玉(=魂)が依りつく巫女的な女性をあらわしています。これらはこの世を訪ねた天上界の男性神が、地上の女神と一体化した人間の女性・巫女と聖婚して豊穣をもたらす農耕儀礼・一夜妻を暗示しています。日向三代を通じて天の力は山や海に降ろされ和合していきます。この問題は勾玉消滅の項でまとめて論じる予定です。
さらにもうひとつ、余談ですが、龍神の気息のうちに結晶化する如意宝珠は、中国では 「龍戯玉」と題され、運気を高め、開運招福する縁起物として彫刻のテーマに選ばれてきました。こうした東洋の伝説と、西洋のカーバンクルの伝説はよく似ています。カーバンクルはドラゴンの脳に析出する伝説の赤い宝石で、現実的にはカボーションカットされたガーネットやルビー、赤い色のスピネルがそう呼ばれて、中近東へ遠征する兵士の守護石になりました。東も西も、古代の呪術は農耕儀礼から発展してきたものなので、基本はあまり違わないと思わせます。